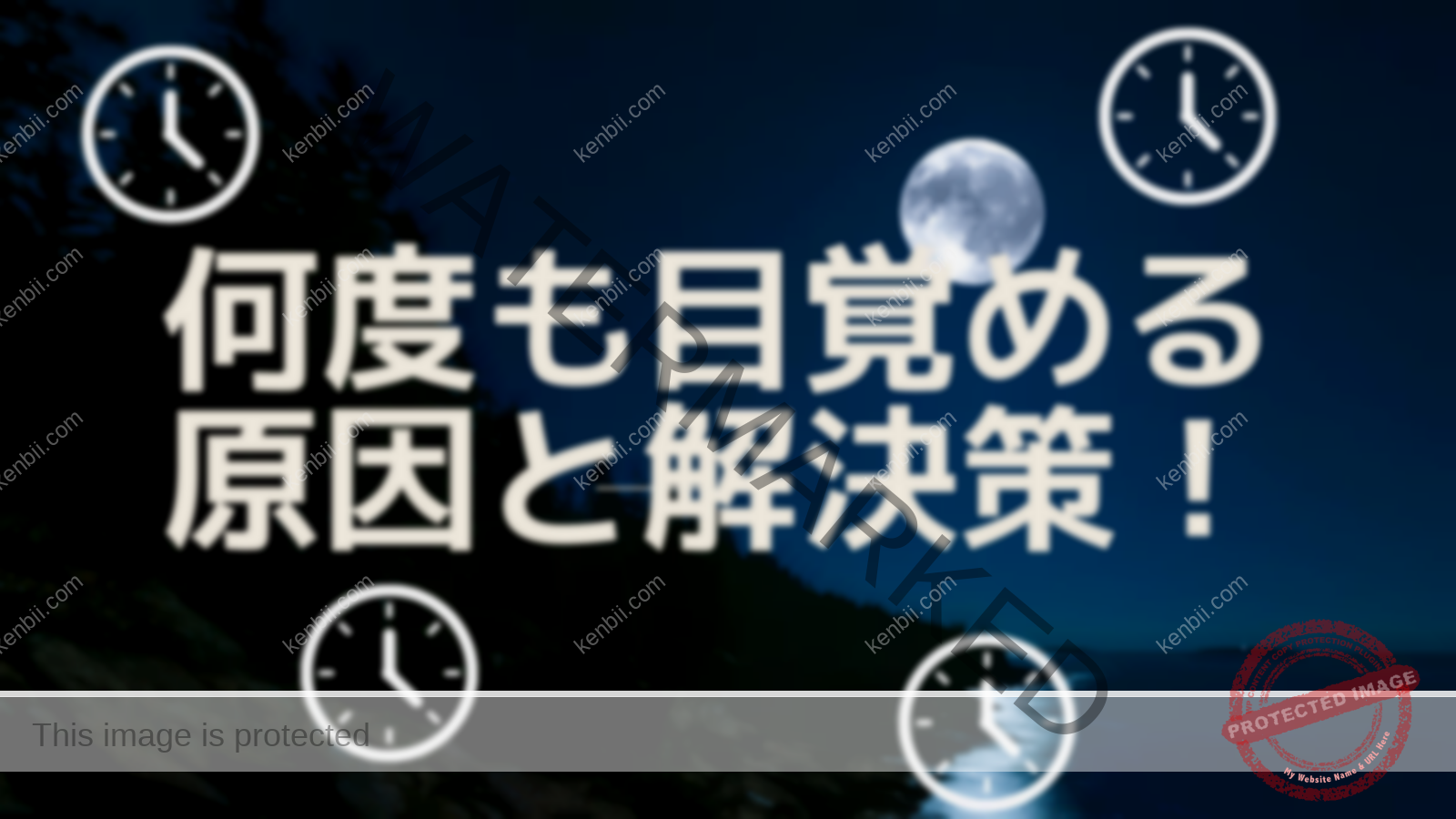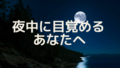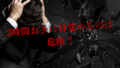「夜中に何度も目が覚めてしまう…」と感じて、不安を抱えている方もいるでしょう。
「朝までぐっすり眠りたいのに、どうして…?」と悩んでいるかもしれません。
夜中に何度も目が覚める原因は、生活習慣の乱れやストレス、睡眠障害などが考えられます。
その原因を特定し適切に対処することで、睡眠の質を向上させることができるでしょう。
まずは、ご自身の睡眠の状態を把握し、何が原因で夜中に目が覚めてしまうのかを考えてみましょう。
原因が特定できれば、対策を講じることが可能です。
この記事では、夜中に何度も目が覚めてしまうことに悩む方に向けて、
– 夜中に何度も目が覚める原因
– 快眠を得るための具体的な方法
– 睡眠環境の改善策
上記について、筆者の経験を交えながら解説しています。
睡眠の質を高めることは、日中のパフォーマンス向上や健康維持に繋がります。
ぜひこの記事を参考にして、快適な睡眠を取り戻してください。
夜中に何度も目が覚める原因とは?
夜中に何度も目が覚めてしまうと、睡眠不足で日中のパフォーマンスが低下したり、寝不足による体調不良に悩まされたりするでしょう。ぐっすり眠りたいのに、なかなかそれが叶わず、どうすれば良いのか分からず困っている方もいるかもしれません。睡眠の質を高めるためには、まず目が覚めてしまう原因を特定することが大切です。
目が覚める原因は様々ですが、例えば寝室の環境や生活習慣、あなたの年齢なども関係しているかもしれません。暑すぎたり寒すぎたりする室温、明るすぎる照明、カフェインの過剰摂取、寝る前のスマホの使いすぎなど、これらは睡眠の質を低下させる要因としてよく挙げられます。また、加齢に伴う身体の変化も、夜中に目が覚めやすくなる原因の一つです。
具体的には、40代以降になると、睡眠ホルモンであるメラトニンの分泌量が減少していくため、夜中に目が覚めやすくなることが知られています。また、更年期障害の症状として、寝汗やほてり、動悸などが現れ、夜中に目が覚めてしまうケースも少なくありません。他にも、睡眠時無呼吸症候群やむずむず脚症候群といった睡眠障害が原因となっている可能性もあります。以下で詳しく解説していきます。
加齢による睡眠の変化
夜中に何度も目が覚める原因とは?
加齢による睡眠の変化
年齢を重ねると、睡眠の質は変化します。ノンレム睡眠の中でも深い睡眠である徐波睡眠の時間が減少し、眠りが浅くなる傾向があります。60代では20代の約半分しか徐波睡眠が現れないという研究結果も出ているほどです。 結果、夜中に何度も目が覚めやすくなってしまうのです。これは自然な老化現象の一つと言えるでしょう。
不眠症の可能性を考える
夜中に何度も目が覚めてしまう、そんな経験はありませんか? 実はこれ、多くの人が抱える睡眠の悩みです。加齢に伴い、睡眠時間は短くなり、夜中に目覚める回数も増える傾向にあります。50代になると、深い睡眠であるノンレム睡眠の時間が減少することが一因です。
もしかしたら、それは不眠症のサインかもしれません。不眠症とは、寝つきが悪い、途中で目が覚める、早く目が覚めてしまうなどの症状が続き、日中の生活に支障をきたす状態です。睡眠時間の長さではなく、睡眠の質が悪く、日中に倦怠感や集中力の低下を感じたら、不眠症を疑ってみましょう。
もちろん、一時的なストレスやプレッシャーも睡眠に影響を与えます。プレッシャーのかかる出来事の前後や、心配事が頭を離れない時などは、夜中に目が覚めやすくなるのはよくあることです。また、寝室の温度や湿度、明るさ、騒音なども安眠を妨げる要因となります。夏場の暑さや冬の寒さ、街灯の明るさや隣家の物音などは、睡眠の質を低下させる可能性があります。
さらに、健康問題が隠れているケースも見過ごせません。夜間頻尿や睡眠時無呼吸症候群、むずむず脚症候群などは、夜中に何度も目が覚める原因となります。特に、40代以降でこれらの症状が現れたら、一度医療機関を受診してみることをおすすめします。
ストレスやプレッシャーの影響
夜中に何度も目が覚める原因とは?
ストレスやプレッシャーの影響
現代社会において、ストレスやプレッシャーは誰しもが抱えるものです。仕事での責任、人間関係の悩み、将来への不安など、様々な要因が睡眠に影響を与えます。ストレスを感じると、交感神経が優位になり、脳が興奮状態になり、寝つきが悪くなったり、夜中に何度も目が覚めてしまうのです。
厚生労働省の調査によると、2022年には約1,400万人が何らかの睡眠の悩みを抱えていると報告されており、ストレスはその大きな要因の一つと考えられています。 過剰なストレスは、コルチゾールというホルモンの分泌を促し、睡眠の質を低下させることが明らかになっています。 例えば、大事なプレゼンテーションの前日や、大きな決断を迫られた時など、緊張や不安から夜中に何度も目が覚めてしまう経験は誰しもあるのではないでしょうか。
また、ストレスが原因の不眠は、自律神経のバランスを崩し、身体にも悪影響を及ぼします。免疫力の低下や、高血圧、糖尿病などの生活習慣病のリスクを高める可能性もあるため、注意が必要です。
寝室環境が快眠を妨げる
夜中に何度も目が覚める原因とは? 加齢に伴い、睡眠は浅くなり、夜中に目覚めやすくなります。また、不眠症も原因の一つです。日中のストレスやプレッシャーも睡眠の質に影響を与え、夜中に目が覚める原因となります。寝室環境も重要です。室温や湿度、明るさ、騒音などは快眠を妨げる要因となります。 加齢以外にも、健康問題が隠れている可能性も考えられます。
寝室環境が快眠を妨げる 快適な睡眠のためには、寝室環境の見直しが重要です。理想的な室温は18~20℃、湿度は50~60%と言われています。光や音も睡眠に影響を与えます。真っ暗な環境が理想ですが、難しい場合はアイマスクを使用するのも良いでしょう。外部からの騒音は耳栓で軽減できます。また、寝具の素材や硬さも重要です。自分に合った寝具を選び、快適な睡眠環境を整えましょう。
健康問題が原因の可能性
夜中に何度も目が覚める原因とは?
加齢による睡眠の変化:年齢を重ねると、睡眠の質は変化します。ノンレム睡眠とレム睡眠のバランスが崩れ、深い睡眠が減少しがちです。50代になると、若い頃と比べて睡眠時間は1時間ほど短くなることも。
不眠症の可能性を考える:睡眠時間や質に問題があり、日中の活動に支障が出る場合は、不眠症の可能性があります。慢性的な睡眠不足は、集中力低下や倦怠感を招き、生活の質を下げてしまうので注意が必要です。
ストレスやプレッシャーの影響:仕事や人間関係のストレス、将来への不安などは、自律神経のバランスを崩し、睡眠に悪影響を及ぼします。ストレスが原因で夜中に何度も目が覚めてしまうケースも多いです。
寝室環境が快眠を妨げる:室温や湿度、寝具、騒音、照明など、寝室環境が睡眠の質を左右します。適切な温度・湿度を保ち、光や音を遮断することで、より良い睡眠を得られるでしょう。
健康問題が原因の可能性:睡眠時無呼吸症候群やむずむず脚症候群、夜間頻尿などは、夜中に何度も目が覚める原因となります。基礎疾患が隠れている可能性もあるので、気になる症状があれば医療機関への受診をおすすめします。
夜中に目が覚めないための改善策
夜中に何度も目が覚めてしまうと、睡眠不足で日中のパフォーマンスが低下してしまいますよね。ぐっすり眠ってスッキリ目覚めるためには、生活習慣の見直しが必要です。睡眠の質を高めるための具体的な方法を、このセクションでご紹介していきます。
睡眠の質を上げるためには、規則正しい生活リズムを維持することが重要です。体内時計を整えることで、自然な睡眠覚醒サイクルを作り出すことができます。また、寝る直前のカフェインやアルコール摂取、スマホのブルーライトは睡眠の妨げになるので控えましょう。適度な運動も効果的ですが、激しい運動は交感神経を優位にしてしまうため、就寝直前は避けましょう。
例えば、毎日同じ時間に起床し、朝日を浴びることで体内時計がリセットされます。夕食は寝る3時間前までに済ませ、就寝1時間前にはリラックスできる時間を作るのがおすすめです。具体的には、ぬめり湯に浸かったり、ハーブティーを飲んだり、アロマを焚いたりするのも良いでしょう。以下で、さらに詳しく解説していきます。
規則正しい睡眠リズムを作る
夜中に何度も目が覚める原因とは? 加齢に伴い、睡眠は浅くなり、夜中に目覚める回数が増える傾向にあります。50代になると、若い頃と比べて深い睡眠の時間が半分以下になることも。 また、不眠症やうつ病などの精神疾患も、睡眠の質を低下させる要因です。 ストレスや不安、プレッシャーも睡眠に悪影響を及ぼします。寝室の温度や湿度、明るさ、騒音なども、快眠を妨げる可能性があります。 さらに、睡眠時無呼吸症候群や周期性四肢運動障害といった健康問題も、夜間覚醒の原因となることがあります。
夜中に目が覚めないための改善策
規則正しい睡眠リズムを作るには、毎日同じ時間に寝起きし、体内時計を整えることが重要です。 朝日を浴びることで、睡眠ホルモンであるメラトニンの分泌が調整され、自然な睡眠サイクルが促されます。 週末も平日と同じような時間に起きるように心がけましょう。
寝る前のリラックスタイムを大切に
寝る前のリラックスタイムは、質の高い睡眠を得るために非常に重要です。副交感神経を優位にすることで、心身ともにリラックスした状態を作り、スムーズな入眠と深い睡眠へと導きます。
具体的な方法としては、ぬるめのお風呂にゆっくり浸かったり、ハーブティーを飲んだり、アロマを焚いたりするのも良いでしょう。読書や瞑想もおすすめです。スマホやパソコンなどのブルーライトは睡眠の妨げになるので、寝る1時間前には使用を控えましょう。
また、軽いストレッチやヨガなども効果的です。就寝前の15~30分程度の軽い運動は、筋肉の緊張をほぐし、血行を促進することで、心地よい眠りを誘います。ただし、激しい運動は逆効果となるので注意が必要です。
自分に合ったリラックスメソッドを見つけて、毎晩寝る前に実践することで、夜中に目が覚めることなく、朝までぐっすり眠れるようになるでしょう。心地よい眠りで、日中のパフォーマンスも向上させることができるはずです。
寝室環境を整えて快適に
寝室環境を整えることは、夜中に何度も目が覚める問題を解決する重要な一歩です。快適な睡眠を得るためには、まず室温を26℃以下、湿度を50~60%に保つことが理想的と言われています。夏はエアコンや除湿機、冬は加湿器を活用し、快適な温度・湿度を維持しましょう。
次に、光を遮断することも大切です。街灯や朝日が睡眠を妨げることがあります。遮光カーテンやアイマスクを活用して、寝室を暗く保つ工夫をしてみてください。寝室の照明も、暖色系の落ち着いた明るさにすると良いでしょう。
また、音にも気を配りましょう。外部からの騒音や、時計の秒針の音など、些細な音が睡眠を妨げることがあります。耳栓を使用したり、寝室に防音カーテンを設置するなどの対策を検討してみてください。さらに、アロマディフューザーでラベンダーなどのリラックス効果のある香りを焚いたり、寝具やパジャマの素材にこだわることも、快適な睡眠へと導いてくれます。
夜間のトイレ対策を考える
夜間のトイレで目が覚めてしまうのは、年齢を重ねるとともに増えていく悩みです。就寝前に水分を摂りすぎないよう、夕食後は控えめにしましょう。また、カフェインやアルコールの利尿作用にも注意が必要です。夕方以降はコーヒーや緑茶を避け、お酒も控えめにすると良いでしょう。就寝2~3時間前には水分摂取を控えるのが理想的です。しかし、脱水症状も睡眠の質を下げるため、日中の水分補給はしっかりと行うことが大切です。どうしても夜中にトイレに行きたくなってしまう場合は、我慢せずにトイレに行く方が、睡眠を妨げずに済みます。ただし、なるべく明るい照明を避け、すぐに布団に戻ることが重要です。トイレに行くことで目が冴えてしまう場合は、寝る前にリラックスできる音楽を聴いたり、アロマを焚いたりするなど、再び眠りにつきやすい環境を作る工夫も有効です。
健康的な食生活を心がける
夜中に何度も目が覚めてしまう、そんな経験はありませんか? 睡眠不足は日中のパフォーマンス低下に繋がり、生活の質を落とす大きな原因となります。加齢に伴い、睡眠は浅くなりがちです。50代になると若い頃と比べて深いノンレム睡眠の時間が減り、夜中に目が覚めやすくなります。また、不眠症も原因の一つ。寝つきが悪い、眠りが浅いなどの症状が1ヶ月以上続く場合は、不眠症の可能性も考えられます。
日中のストレスやプレッシャーも睡眠の質に影響を与えます。仕事での悩みや人間関係のトラブルを抱えていると、リラックスできず夜中に何度も目が覚めてしまうことも。寝室環境も重要です。室温や湿度、照明、騒音などは、快眠を妨げる要因となります。快適な睡眠を得るためには、寝室環境を整えることが大切です。
さらに、健康問題が隠れている可能性も。睡眠時無呼吸症候群や、頻尿、夜間頻尿などは夜中の覚醒の原因となります。生活習慣を見直し、健康的な食生活を心がけましょう。例えば、寝る直前のカフェイン摂取や夕食の食べ過ぎは、睡眠の質を低下させる可能性があります。バランスの良い食事を心がけ、就寝前の飲食は控えめにすると良いでしょう。
不眠が続くとどうなる?放置するリスク
夜中に何度も目が覚めてしまうと、日中のパフォーマンス低下につながるなど、心身に大きな負担がかかります。睡眠不足が慢性化すると、集中力の低下や倦怠感といった症状に悩まされるでしょう。
不眠が続くと、身体の免疫機能が低下し、風邪などの感染症にかかりやすくなります。また、自律神経のバランスが崩れ、めまいや動悸、頭痛などの身体的な不調が現れる場合もあります。精神面でもイライラしやすくなったり、気分が落ち込んだりするなど、情緒不安定に陥る可能性が高まります。高血圧や糖尿病などの生活習慣病のリスクも高まるため、決して放置してはいけません。
例えば、睡眠不足が続くと、ホルモンバランスが乱れ、食欲をコントロールするホルモンの分泌に影響を与えます。その結果、過食につながり、肥満のリスクを高める可能性があるでしょう。具体的には、成長ホルモンの分泌が阻害されることで、肌の老化を促進したり、筋肉量の減少を招いたりするケースも報告されています。以下で詳しく解説していきます。
健康への影響と病気のリスク
夜中に何度も目が覚めてしまうと、日中の倦怠感や集中力の低下につながり、生活の質を大きく下げてしまいます。睡眠不足が続くと、様々な健康問題のリスクも高まります。今回は、夜中に目が覚める原因と、その改善策、そして放置した場合のリスクについて解説します。
加齢に伴い、睡眠は浅くなり、夜中に目が覚めやすくなる傾向があります。50代になると、深いノンレム睡眠の時間が20代の約半分になってしまうというデータもあります。 また、不眠症も原因の一つです。寝つきが悪い、途中で目が覚める、早く目が覚めてしまうといった症状が慢性的に続く場合は、不眠症の可能性を疑いましょう。
ストレスや不安、過度なプレッシャーも睡眠の質を低下させます。寝る直前までスマートフォンやパソコンを使用すると、ブルーライトの影響でメラトニン分泌が抑制され、睡眠の質が低下する可能性も。寝室の温度や湿度、明るさ、騒音なども睡眠に影響を与えます。快適な睡眠環境を整えることが重要です。
高血圧や糖尿病、睡眠時無呼吸症候群などの健康問題が、夜中に目が覚める原因になっているケースもあります。 睡眠不足が続くと、免疫力の低下や生活習慣病のリスクが高まるだけでなく、うつ病などの精神的な不調につながる可能性も懸念されます。症状が続く場合は、心療内科や睡眠外来を受診し、専門医に相談しましょう。
精神的な不調を引き起こす可能性
夜中に何度も目が覚めてしまうと、日中の倦怠感や集中力の低下につながり、日常生活に大きな支障をきたします。この不眠の状態が続くと、肉体的にも精神的にも悪影響を及ぼす可能性があります。
睡眠不足は免疫機能を低下させ、風邪などの感染症にかかりやすくなります。また、高血圧や糖尿病などの生活習慣病のリスクも高まると言われています。厚生労働省の調査によると、睡眠時間が短い人ほどこれらの病気の発症率が高いという結果も出ています。
さらに、不眠は精神的な不調にもつながることがあります。睡眠不足が続くと、イライラしやすくなったり、気分が落ち込んだりするなど、情緒不安定になりやすいです。慢性的な不眠は、うつ病などの精神疾患のリスクを高める可能性も指摘されています。例えば、2018年の国民健康・栄養調査では、睡眠時間が6時間未満の人は、7時間以上の人に比べて、抑うつ症状のリスクが約1.5倍高いという結果が出ています。夜中に何度も目が覚めることで、不安や焦燥感が増し、精神的な負担が大きくなる場合もあるでしょう。適切な睡眠をとることは、心身の健康を保つ上で非常に重要です。
専門医に相談するタイミング
夜中に何度も目が覚めてしまうと、日中の倦怠感につながり、生活の質を低下させてしまうでしょう。睡眠の質を改善するために、まずは自分でできる対処法を試してみるのが良いですが、中には専門医への相談が必要なケースもあります。
専門医に相談するタイミングは、セルフケアを試しても2週間以上症状が改善しない場合です。睡眠の質の低下が慢性化すると、仕事や日常生活に大きな支障をきたす可能性があります。睡眠障害は様々な原因が考えられるため、自己判断で対処を続けるよりも、専門家の適切な診断とアドバイスを受けることが重要でしょう。
例えば、睡眠時無呼吸症候群のような疾患が隠れているかもしれません。また、精神的なストレスや生活習慣の乱れが原因で睡眠の質が低下しているケースもあります。このような場合は、専門医による適切な治療やカウンセリングを受けることで、根本的な改善につながることが期待できます。以下で、専門医に相談すべき症状や受診する診療科について詳しく解説していきます。
どのような症状が要注意か
夜中に何度も目が覚めてしまう、その原因を探る手がかりとなる症状をチェックしてみましょう。
まず、中途覚醒に加えて、日中の強い眠気や倦怠感、集中力の低下といった症状が現れている場合は、注意が必要です。単なる睡眠不足ではなく、睡眠の質そのものが低下している可能性があります。例えば、睡眠時無呼吸症候群では、睡眠中に呼吸が何度も止まり、その度に脳が覚醒するため、熟睡感が得られません。結果として、日中に強い眠気を引き起こすのです。
また、寝つきが悪い、なかなか眠れないといった入眠困難や、早朝に目が覚めてしまい二度寝できないといった早期覚醒も、睡眠障害のサインかもしれません。これらの症状に加えて、イライラしやすくなったり、気分が落ち込んだりするといった精神的な変化も併発する場合は、専門医への相談が必要になります。
さらに、胸やけ、動悸、頻尿、足のむずむず感など、身体的な不快感が原因で目が覚める場合も、基礎疾患が隠れている可能性があるので、注意が必要です。自己判断せず、医療機関を受診し、適切なアドバイスを受けるようにしましょう。特に、50歳を超えてから夜間頻尿が急に増えた場合は、前立腺肥大症などの病気が潜んでいる可能性も考えられます。
心療内科や睡眠外来の活用
夜中に何度も目が覚めてしまう、そんな悩みを抱えていませんか? 不眠の原因は様々ですが、年齢を重ねると睡眠の質が変化することもあります。 40代になると成長ホルモンの分泌が減少するため、深い睡眠が得にくくなるのです。 また、ストレスや不安、寝室の環境なども影響します。
心療内科や睡眠外来を受診することで、睡眠の質を改善する具体的な方法を見つけることができます。睡眠外来では、睡眠日誌をつけたり、PSG検査(終夜睡眠ポリグラフ検査)などを通して睡眠の状態を詳しく調べ、原因に合わせた治療法を提案してくれます。睡眠薬の処方も可能ですが、依存性や副作用のリスクも考慮し、医師と相談しながら慎重に使用する必要があります。 心療内科では、睡眠障害の背景にある心理的な要因を探り、認知行動療法などを通して根本的な解決を目指します。 例えば、過剰な心配や不安が睡眠を妨げている場合は、その原因に対処することで睡眠の質を改善できる可能性があります。 自己判断で市販の睡眠薬を服用するのではなく、専門家のアドバイスを受けることで、より適切な対処法を見つけ、快適な睡眠を取り戻せるはずです。
夜中に目が覚める悩みに関するQ&A
夜中に何度も目が覚めてしまうと、睡眠不足で日中のパフォーマンスが低下したり、不安を感じたりする方もいるでしょう。このセクションでは、よくある疑問に答える形で、その原因や対策について解説していきます。具体的な例を挙げながら説明することで、より理解を深めていただけます。
睡眠に関する悩みは人それぞれですが、多くの方が抱える共通の悩みも存在します。夜中に目が覚める回数や時間帯、その後の寝付きやすさなどは個人差がありますが、背景にある原因や対処法を知ることで、より良い睡眠を得られる可能性が高まります。睡眠の質を向上させるための第一歩として、よくある疑問とそれに対する回答を理解しておきましょう。
例えば、「加齢とともに夜中に目が覚めやすくなるのはなぜ?」という質問に対しては、体内時計の変化やホルモンバランスの乱れ、身体機能の低下などを要因として挙げることができます。また、「寝る前にカフェインを摂ると夜中に目が覚めるって本当?」という疑問には、カフェインの覚醒作用が睡眠を妨げる可能性があると説明できます。以下で詳しく解説していきます。
夜中に目が覚めるのは普通?
夜中に何度も目が覚めてしまうのは、一体何が原因なのでしょうか。 加齢とともに睡眠は浅くなり、夜中に目覚める回数が増える傾向にあります。40代を過ぎると、成長ホルモンの分泌が減少するため、深い睡眠を取りにくくなるのです。
しかし、年齢だけが理由とは限りません。 頻繁に夜中目が覚める、日中に強い眠気を感じるといった症状が続く場合は、不眠症の可能性も考えられます。 また、仕事や人間関係によるストレス、プレッシャーも睡眠の質を低下させる大きな要因です。
さらに、寝室の温度や湿度、明るさ、騒音なども快眠を妨げることがあります。 快適な睡眠環境を整えることは、夜中に目が覚める問題を解決する第一歩です。
他に、睡眠時無呼吸症候群などの健康問題が隠れているケースもあるため、注意が必要です。 生活習慣を見直しても改善が見られない場合は、医療機関への相談も検討しましょう。
改善策を試しても効果がない時は?
夜中に何度も目が覚めてしまう、そんな悩みを抱えていませんか? 加齢とともに睡眠は浅くなる傾向があり、50代以降は特に顕著になります。しかし、年齢だけが原因とは限りません。ストレスや不安、寝室の環境、カフェインの過剰摂取、さらには睡眠時無呼吸症候群などの健康問題が隠れている可能性も考えられます。
もし、様々な改善策を試しても効果がない場合はどうすれば良いでしょうか? 睡眠日記をつけて自分の睡眠パターンを把握したり、就寝前のルーティンを見直してみましょう。それでも改善が見られない場合は、専門医への相談も視野に入れてください。睡眠不足が続くと、日中の集中力低下や倦怠感だけでなく、高血圧や糖尿病などの生活習慣病のリスクも高まります。
まずは、生活習慣の改善から始めてみましょう。毎日同じ時間に寝起きする、寝る前にカフェインやアルコールを摂取しない、適度な運動をするなど、基本的なことを実践することが大切です。睡眠環境も見直してみましょう。寝室の温度や湿度、照明、寝具などを調整することで、より快適な睡眠を得られるかもしれません。自分だけで抱え込まず、専門家のサポートも検討してみてくださいね。
まとめ:夜中に目が覚めてしまう原因と対策
今回は、夜中に何度も目が覚めてしまうことに悩む方に向けて、
– 睡眠のメカニズム
– 考えられる原因
– 快眠のコツ
上記について、筆者の経験を交えながらお話してきました。
夜中に何度も目が覚める原因は、ストレスや生活習慣の乱れ、睡眠環境の悪さなど、人によって様々です。こうした原因を特定し、適切な対策を講じることで、睡眠の質を向上させることができるでしょう。
あなたはこれまで、ぐっすり眠りたいと、様々な方法を試してきたかもしれません。もしかしたら、もう諦めかけている方もいるかもしれません。ですが、快眠は決して不可能ではありません。
睡眠の質を高めるための第一歩は、まず自分の睡眠パターンを把握することです。睡眠日誌をつけたり、スマートウォッチなどのデバイスを活用したりするのも良いでしょう。
きっとあなたは、質の高い睡眠を得て、心身ともに健康な毎日を送ることができるはずです。
まずはできることから始めて、快適な睡眠を手に入れていきましょう。具体的な方法としては、寝る前にカフェインを摂らない、適度な運動をする、寝室の温度と湿度を調整するなどがあります。ぜひ試してみてください。